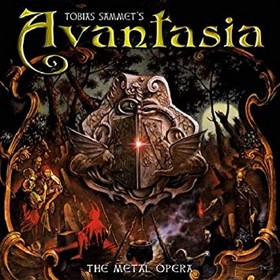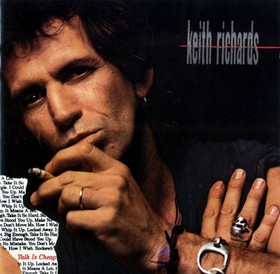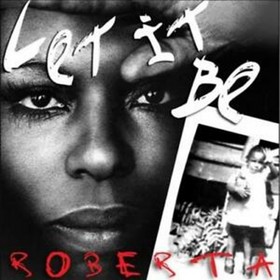2019年!印象に残った作品;Rock編 [音源発掘]
令和を迎えた2019年も、閉幕のカウント・ダウンも始まったところ。
振り返ってみれば令和を迎えた2019年、千葉県民である私にとって、大きく記憶に残っているのが、気象観測史上始まって以来となる、関東・東北を襲った超巨大勢力を有した台風の襲来。
私自身、多くの台風が襲来する鹿児島に住んだことをきっかけに、以前より日本に襲い来る台風の動きを観察していたのですが、ここ数年は、これまで見られなかった異常な動きをすする台風が増えていて、この調子では一部報道機関が報じる通り、沖縄・南九州を襲うに匹敵するまたは以上の強力な台風が関東に上陸する現実も、既に時間の問題だなと、つねづね思ってはいたのですけど。
ところが、それがその予想以上に早く、なんと今年にやって来た!!!!1
このこと、私の想定ではもう少し先のことだと考えていたのに、それが現実に、想定を超える気象状況の急速な変化が今、日本列島の周りで起きているのか????
たった1度乃至2度程度上昇のことなのに、多分に温暖化の影響があるとはいえ、その温暖化克服もまだまだ五里霧中の中、この分では、令和2年目を迎える来年も、同様の災害が発生するのではと、明けて令和の年の瀬に来て、今以上にしっかりと、その備えをしなければと考えさせられることになってしまいました。
のっけから少々重い話となってしまいましたが.............(相すみません!)
とかなんとかで、ここで本題....................................、
今回は、これまでに引き続き”2019年!印象に残った作品”のRock編です。
さすがに入院とあいなった時は、ロック、特にHMは体に堪えるということもあって、聴くのを自重していたのですが、やはり、ロックとなればHM、これを聴かずしては語れるか![[雷]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/5.gif) とあって、体力が回復するのを待って、このロック編、後回しにして来たのですが、徐々に体力も回復、その激しさも心地よく聴けるようになったところで、いよいよ筆を執ることにいたしました。
とあって、体力が回復するのを待って、このロック編、後回しにして来たのですが、徐々に体力も回復、その激しさも心地よく聴けるようになったところで、いよいよ筆を執ることにいたしました。
こちらの方は、今年、波乗って多くの作品に接し楽しむことが出来たジャズ作品とは裏腹に、半年過ぎて自分の目指す方向性がつかめず、おかげで長い間、これは!という作品に出会えることなくいたのですが、夏の終わりごろから、やっとのことで自分の好みにフィットした作品が見つかるようになり、終わってみればこちらの方も3作品を選ぶにあったって絞りがたく結構迷ってしまったといのがその次第。
考えた挙句、今回は、その中で、それぞれに毛色の異なった作品を1作品ずつ選びことで取りまとめをすることにいたしました。
その最初の作品は!!、
当然、「ロックとなればHM」と豪語した、そのメタル作品から..........
ドイツのパワーメタルバンドEdguyのシンガー兼主軸ソングライターである Tobias Sammetが主宰するスーパーグループプロジェクトAvantasia 2001年発表の彼ら最初のフルアルバム ” The Metal Opera Part 1”といたしました。
ドイツというと、こと音楽については、クラッシク音楽のメッカという印象が強いよう場所のように思うのですが、ロックの世界でも1970年代に登場したScorpionsや80年代のACCEPT、そして80年代後半、ジャーマン・メタルの地位を世界に印象付けたHelloweenなどを輩出、高い評価を受けているバンドを多く輩出している、HMの隆盛が思い浮かぶお国柄。
であればScorpions登場以来、メタルも40年余り、であれば現在は、伝統のクラシックと巧み昇華しクラシカルなセンスを以生かせる、いわばシンフォニックなメタル・サウンドを想像出来る連中もいるはずと、探してみたところ、見つけたのがこのAvantasia 2019年発表の最新作”Moonglow”という作品。
聴いてみると、HMらしく強烈なリズムの上を疾駆する分厚く重厚なサウンドを放ちながらなも、クラシックの耽美さと気品が感じられる音楽が、そこから耳に届いて来たのです。
スペインのDark MoorやイタリアのRhapsody Of Fireで、シンフォニック・メタルの世界が気に入り、これまでそのサウンドに聴き浸っていた私にとって、ここ近年は、この2つのバンドもマンネリ化の兆しがみえて来ていて、新作の出来も今一つの感であったから、フラストレーションが溜まってしまい、その感を吹き飛ばしてくれる痛快なかつ重厚緻密なサウンドはないものかと考えていたところのこの出会い。
これは!!!! ということで、彼らの最新作に至る以前の作品を調べてみたところ、興味を惹かれたのがこの彼らの最初のフルアルバムだったのです。
そして、さらに、そのバイオグラフィも調べてみたところ、その始まりはTobias Sammetの発案による多くのゲスト・アーティストをフュチヤーしたメタルオペラ・プロジェクトだったということ。
これは、是非聴いてみなければいけないと思い、ゲスト・アーティストの顔ぶれを追ってみると....、
処女作である本作では、ゲスト・ヴォーカストとして元Helloween 、 現Unisonicのヴォーカリスト Michael Kiske 、Within Temptationの女性ヴォーカリスト Sharon Janny den Adel やGamma Rayの創設者でギタリストでボーカルのKai Michael Hansen 等の名も見え、その後も元KamelotのRoy Khanや Symphony XのRussell Allen 創設時RainbowのJoe Lynn Turner Ritchie Blackmoreの夫人でBlackmore's NightのCandice Night 等、またインストメンタル・プレヤーとしては、Gamma RayのギタリストHenjo Richter、HelloweenのベーシストのMarkus Grosskopf、イタリアのシンフォニック・メタル・バンドのRhapsody of Fireの元メンバーであるドラムのAlex Holzwarth、90年代以降の Kiss のドラムEric SingerやScorpions創設メンバーでギタリストのRudolf Schenker 等、世界のメタル界を代表する爽々たる面々の名が並んでいたのです。
こうなると、Tobias Sammet率いるこのプロジェクト、やはりその出発点から聴いて見なければという思いがますます強くなり、とうとう手に入れてしまっのが、この作品だったという訳なのです。
そして、聴いみての感想は、
どの曲も似たような感じで聴き終えて印象に残るものがなにもなかったと感じるメタル作品が少なくない中、それぞれ曲に明瞭な個性が感じられ、場面々のイメージが映像となって浮かんでくる展開は、まさにメタルオペラという名を冠するに値するものだったというのが、その感想。
しかしその感覚、その微細には、言葉だけではなかなか語り尽くせない、ということでやはりここで1曲、そのインプレッション、聴いていただき感じていただこうかと思います。
お聴きいただく曲は”Sign Of The Cross”です。
ここ近年で私のさもお気に入りのメタルとなった、このAvantasia。
私事かもしれませんが、あらためてジャーマン・メタルの底力、今年は心底思い知らされることなったような気がしています。
この分では私のとって来年も、このAvantasia、さらに続けて聴きあさる事になりそうです。
さて、2つ目の作品は。
次は、プログレシッブ・ロックの作品から
こちらもAvantasia同様、最近よく聴いているバンドの一つである英国のプログレシッブ・バンドのBig Big Train。
その彼らの作品で、今回選んだのは、2017年発表の彼らの9作目となる”Folklore”です。
このバンド、私としては、以前からその名は知ってはいたのですが、いかんせん彼らの作品のアルバム・ジャケットのデザインが好きなれないというサウンドと無関係な理由から、聴くのをためらい続けることしまっていたのです。
ところが、今年になって自分にフィットするロック作品を探すもなかなか見つけることが出来ずに行き詰っていたことから、ジャケットは気に入らないけど、試にプログレッシブ・ロックの本場、英国のバンド、もしかするとという思いで、ならば一度聴いてみるかとの軽い調子そのサウンドに耳を傾けたところ、それが見事に私の好みにフィットしてしまい、完全に彼らの世界に惹きこまれてしまうことになってしまったのです。
1曲々が異なった表情を持つ豊かな曲想、ロック・バンドでは数少ないフルートやヴァイオリンなどのプレヤーを配した緻密で繊細な表現力豊かなサウンド。
プログレシッブ・ロック隆盛の70年代より数多くのプログレシッブ・ロック・バンドを聴いていた私ですが、その完成度の高さは絶品の感が漂うもの。
また加えて、往年のプログレシッブ・ロックでは珍しいヴォーカル・ハーモニーの美しさは、効果的で聴く者の心を労わり優しく包み込み行くような優しさを感じるなど、そうしたことから、これぞ私の望んでいた究極のプログレとの思いを深くすることになっってしまったのです。
それでは、そうした彼らのサウンドここで1曲、聴いてみて下さい。
曲は、本作品の表題曲”Folklore”です。
本作をはじめ彼らの作品のいくつかを聴いて感じたのは、曲中のところどころに70年代を席巻したGenesis、Jethro Tull、CamelそしてPink Floyd等の、往年のプログレのスパースター達の音の断片がさりげなく散りばめられているように感じ、思わずニンマリ、しかし、聴き終われば彼ら独自の音世界の中浸っていた自分に気付くことしばし、70年代以来、本当に久々に出会った私の待ち望んでいた好みのプログレ・サウンド、先のAvantasiaと共に、来年も嵌り続けることになりそうです。
そして、最後の作品は、
前2作の嵌り初め続きの後は、さらに私がロックを聴き始めて以来、数十年間、嵌り続けぱっなしのこの方の作品から。
keith richards talk is cheap keith richards
写真を見て、もうお分かりですね。
そう、Rollinng Stonesギタリスト、Keith Richardsですね。
とは言っても、これはRollinng Stonesの作品ではなくて、これは、Keith Richards 1988年の制作のファースト・ソロ作品である”Take Is So Hard”。
Keithという人、これまでRollinng Stonesの中で、Mich Jaggerのバックでのバッっキング・ヴォーカルを務めていることはよく知られていますけど、実はそれだけはでなく、僅かではあるもリード・ヴォーカルをとった曲も発表してきているのです。
そうしたStonesの中で彼のリード・ヴォーカル、私の場合、その味に嵌ったのは、Stonesの1972年の作品”Exile On Main Street(邦題;メインストリートのならず者)”の中の”Happy”という曲での、その渋くニヒル漂う、いかにもロックン・ローラーとうべきヴォーカルのカッコ良さが忘れられず、以来、意識の奥底にKeith のソロ・ヴォーカル曲を聴いてみたいな思いが宿り続けていたもの。
それが今年、これも自分にフィットするロック作品が見つけようとして、何かないかとパラパラとネットのぺーいををめくり探していたところ突然目に飛び込んで来たのがこの作品で、思わず意識の奥底にあった願望が蘇り即Getしてしまったのがこの作品だったのなのです。
さて、この作品、聴いてみるとサウンド全体としては表面的にはStonesを連想させてしまうものなのですけど、よくMickがリードをとる本来のStonesサウンドと聴き比べてみると、ギターの乗りはStonesであるけれど、前者がR&B的なものを感じるのに対し、全体としてはソリッド感が強くよりロックン・ロール的色彩が濃いく感じられるように思うのです。
そう感じるのは、やはりMickに相似しているよう感じるKeith のヴォーカル、しかし、本質的には異なるその個性にその因であるようで、Mickのヴォーカルにある粘りっこさに変わって、Keithの渋くニヒル漂うヴォーカルが、そうした印象を生んでいるように思うのです。
それでは、Keithの歌うロックン・ロール色濃いStonesサウンドから1曲聴いてみましょう。
曲は、”Take It So Hard”です。
だいぶ昔のことになりますが、私はMickの来日ソロ・ライブを見たことがあるのですが、そこで感じたMickが歌っっていたStnesナンバーの大いなる違和感のこと。
ヴォーカルはMickなれど、なにか妙に明るくてStonesと全く異なったフィーリング、そこに嫌悪、不快感すら覚えた思い出があるのです。
こう考えると、唯一無二と言われるStonesのサウンドは、MickとKeithの独特な個性にCharlie Wattsの重く正確なリズムを刻むドラムが絡み 生まれ出てたもの。
このKeithのソロ作品を聴いてみると、そこのことをあらためて強く感じます。
それにしても、Keithは見て暮れは当然、サウンドのカッコ良さも抜群。
年とる毎に、男のカッコ良さが滲み出て来るような、70歳を過ぎた写真の彼もそうでした。
こうした年取り方、私も彼にあやかりたいものだと、聴きながらそんなことを考えてしまいました。
それでは、最後にこの作品から、Keithの渋いロッカー・バラード” Make no mistake”で令和初年の音楽談義を締め括ることにしたいと思います。
来るべき令和2年も良い年でありますように。
Avantasia:The Metal Opera
Track listing
All tracks are written by Tobias Sammet.
1. Prelude
2. Reach Out for the Light
3. Serpents in Paradise
4. Malleus Maleficarum
5. Breaking Away
6. Farewell
7. The Glory of Rome
8. In Nomine Patris
9. Avantasia
10. A New Dimension
11. Inside
12. Sign of the Cross
13. The Tower" Kiske
Personnel
Tobias Sammet (Edguy) - Keyboards, Vocals (see "Singers")
Henjo Richter (Gamma Ray) - Guitars
Markus Grosskopf (Helloween) - Bass guitar
Alex Holzwarth (Rhapsody of Fire) - Drums
Guests Musicians
Guitar Jens Ludwig (Edguy) (lead on tracks 12 & 13)
Norman Meiritz (acoustic on track 6)
Keyboards Frank Tischer (Piano on track 11)
Guests Singers
Gabriel Laymann – Tobias Sammet (Edguy) - tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 & 13
Lugaid Vandroiy – Michael Kiske (credited as Ernie) (ex-Helloween, Unisonic) - tracks 2, 5, 6, 9, & 13
Friar Jakob – David DeFeis (Virgin Steele) - tracks 3 & 13
Bailiff Falk von Kronberg – Ralf Zdiarstek - tracks 4 & 7
Anna Held – Sharon den Adel (Within Temptation) - track 6
Bishop Johann von Bicken – Rob Rock (ex-Axel Rudi Pell, Driver, Impellitteri) - track 7 & 12
Pope Clement VIII – Oliver Hartmann (ex-At Vance) - tracks 7, 12 & 13
Elderane the Elf – Andre Matos † (ex-Symfonia, ex-Shaaman, ex-Angra, Viper) – tracks 11, 12 & 13
Regrin the Dwarf – Kai Hansen (Gamma Ray, ex-Helloween) - tracks 11 & 12
Voice of the Tower – Timo Tolkki (ex-Symfonia, ex-Revolution Renaissance, ex-Stratovarius) - track 13
Recorded
2000 Rhoen Studios, Germany
Big Big Train:Folklore
Track listing
1. Folklore -David Longdon-
2. London Plane -Greg Spawton-
3. Along the Ridgeway -Spawton-
4. Salisbury Giant -Spawton-
5. The Transit of Venus Across the Sun -Spawton-
6. Wassail -Longdon-
7. Winkie -Longdon-
8. Brooklands -Spawton-
9. Telling the Bees -Longdon-
Personnel
David Longdon - lead vocals, flute, acoustic guitar, mandolin, percussion
Nick D'Virgilio - drums, percussion, backing vocals
Greg Spawton - bass guitar, bass pedals, acoustic guitar, backing vocals
Andy Poole - acoustic guitar, mandolin, keyboards, backing vocals
Dave Gregory - electric guitars
Danny Manners - keyboards, double bass
Rachel Hall - violin, viola, cello, backing vocals
Rikard Sjöblom - keyboards, electric guitars, accordion, backing vocals
Released
27 May 2016
keithe Richards:Take Is So Hard
Track listing
All songs by Keith Richards and Steve Jordan.
1.Big Enough
2.Take It So Hard
3.Struggle
4.I Could Have Stood You Up
5.Make No Mistake
6.You Don't Move Me
7."How I Wish
8.Rockawhile
9.Whip It Up
10.Locked Away
11.It Means a Lot
Personnel
The X-Pensive Winos
Keith Richards – lead vocals, guitar
Steve Jordan – drums, percussion, bass on 'Take It So Hard', backing vocals
Sarah Dash – backing vocals, duet on "Make No Mistake"
Charley Drayton – bass guitar, drums on 'Take It So Hard'
Ivan Neville – piano, keyboards
Bobby Keys – tenor saxophone on "I Could Have Stood You Up" and "Whip It Up"
Waddy Wachtel – acoustic, electric, and slide guitar, production consultant
Additional musicians
Bootsy Collins – bass guitar on "Big Enough"
Michael Doucet – violin on "Locked Away"
Stanley "Buckwheat" Dural – accordion on "You Don't Move Me", "Rockawhile" and "Locked Away"
Johnnie Johnson – piano on "I Could Have Stood You Up"
Chuck Leavell – organ on "I Could Have Stood You Up"
Maceo Parker – alto saxophone on "Big Enough"
Joey Spampinato – bass guitar on "I Could Have Stood You Up" and "Rockawhile"
Mick Taylor – guitar on "I Could Have Stood You Up"
Bernie Worrell – organ on "Big Enough" and "You Don't Move Me", clavinet on "Make No Mistake" and "Rockawhile"
Jimmi Kinnard – bass guitar on "Make No Mistake"
Patti Scialfa – backing vocals
The Memphis Horns – horns
Willie Mitchell – horn arrangements
Recorded
August 1987 – May 1988
PS.
令和元年の今年で印象に残り感じたこと。
それは、昭和、平成、そして令和と3代の天皇を見て来た私にとって、この令和のさまざま新天皇の即位の儀式に対し、それに接する国民の態度の対応の新旧における大きな違いこと。
昭和の天皇は、戦後国民の象徴となったとは言え、その責務を果たそうするも、自身があの戦争渦中にあってそれを阻止出来なかった回顧の思いからか、今一つ国民とは別次元の存在を払拭出来なかったように思え、その後、そうした名残が現上皇様、天皇即位の際もまだ多分に残っていたよう感じたのに対し、今年の現天皇の即位の折は、真に国民の中にその存在が根付き定着していたと感じたこと。
一昔前のように天皇は神ではなく(あれは、欧米先進国の侵略を防ぐ強い集権国家を作るための明治の元勲たちの知恵から生まれた歴史的必然性だったと考えるのですが。)、平和、この国の人々の安定した生活を営むためシンボルとして、その存在が定着したということではと感じ、これからもそうあり続けて欲しいとの願いをあらたした。
たかが30年間なのに、その行動考え方次第で、自分を含め人々の思いがここまで変わるものだということを知らされたこと、これは本当に大きな心の収穫でした。
振り返ってみれば令和を迎えた2019年、千葉県民である私にとって、大きく記憶に残っているのが、気象観測史上始まって以来となる、関東・東北を襲った超巨大勢力を有した台風の襲来。
私自身、多くの台風が襲来する鹿児島に住んだことをきっかけに、以前より日本に襲い来る台風の動きを観察していたのですが、ここ数年は、これまで見られなかった異常な動きをすする台風が増えていて、この調子では一部報道機関が報じる通り、沖縄・南九州を襲うに匹敵するまたは以上の強力な台風が関東に上陸する現実も、既に時間の問題だなと、つねづね思ってはいたのですけど。
ところが、それがその予想以上に早く、なんと今年にやって来た!!!!1
このこと、私の想定ではもう少し先のことだと考えていたのに、それが現実に、想定を超える気象状況の急速な変化が今、日本列島の周りで起きているのか????
たった1度乃至2度程度上昇のことなのに、多分に温暖化の影響があるとはいえ、その温暖化克服もまだまだ五里霧中の中、この分では、令和2年目を迎える来年も、同様の災害が発生するのではと、明けて令和の年の瀬に来て、今以上にしっかりと、その備えをしなければと考えさせられることになってしまいました。
のっけから少々重い話となってしまいましたが.............(相すみません!)
とかなんとかで、ここで本題....................................、
今回は、これまでに引き続き”2019年!印象に残った作品”のRock編です。
さすがに入院とあいなった時は、ロック、特にHMは体に堪えるということもあって、聴くのを自重していたのですが、やはり、ロックとなればHM、これを聴かずしては語れるか
こちらの方は、今年、波乗って多くの作品に接し楽しむことが出来たジャズ作品とは裏腹に、半年過ぎて自分の目指す方向性がつかめず、おかげで長い間、これは!という作品に出会えることなくいたのですが、夏の終わりごろから、やっとのことで自分の好みにフィットした作品が見つかるようになり、終わってみればこちらの方も3作品を選ぶにあったって絞りがたく結構迷ってしまったといのがその次第。
考えた挙句、今回は、その中で、それぞれに毛色の異なった作品を1作品ずつ選びことで取りまとめをすることにいたしました。
その最初の作品は!!、
当然、「ロックとなればHM」と豪語した、そのメタル作品から..........
ドイツのパワーメタルバンドEdguyのシンガー兼主軸ソングライターである Tobias Sammetが主宰するスーパーグループプロジェクトAvantasia 2001年発表の彼ら最初のフルアルバム ” The Metal Opera Part 1”といたしました。
ドイツというと、こと音楽については、クラッシク音楽のメッカという印象が強いよう場所のように思うのですが、ロックの世界でも1970年代に登場したScorpionsや80年代のACCEPT、そして80年代後半、ジャーマン・メタルの地位を世界に印象付けたHelloweenなどを輩出、高い評価を受けているバンドを多く輩出している、HMの隆盛が思い浮かぶお国柄。
であればScorpions登場以来、メタルも40年余り、であれば現在は、伝統のクラシックと巧み昇華しクラシカルなセンスを以生かせる、いわばシンフォニックなメタル・サウンドを想像出来る連中もいるはずと、探してみたところ、見つけたのがこのAvantasia 2019年発表の最新作”Moonglow”という作品。
聴いてみると、HMらしく強烈なリズムの上を疾駆する分厚く重厚なサウンドを放ちながらなも、クラシックの耽美さと気品が感じられる音楽が、そこから耳に届いて来たのです。
スペインのDark MoorやイタリアのRhapsody Of Fireで、シンフォニック・メタルの世界が気に入り、これまでそのサウンドに聴き浸っていた私にとって、ここ近年は、この2つのバンドもマンネリ化の兆しがみえて来ていて、新作の出来も今一つの感であったから、フラストレーションが溜まってしまい、その感を吹き飛ばしてくれる痛快なかつ重厚緻密なサウンドはないものかと考えていたところのこの出会い。
これは!!!! ということで、彼らの最新作に至る以前の作品を調べてみたところ、興味を惹かれたのがこの彼らの最初のフルアルバムだったのです。
そして、さらに、そのバイオグラフィも調べてみたところ、その始まりはTobias Sammetの発案による多くのゲスト・アーティストをフュチヤーしたメタルオペラ・プロジェクトだったということ。
これは、是非聴いてみなければいけないと思い、ゲスト・アーティストの顔ぶれを追ってみると....、
処女作である本作では、ゲスト・ヴォーカストとして元Helloween 、 現Unisonicのヴォーカリスト Michael Kiske 、Within Temptationの女性ヴォーカリスト Sharon Janny den Adel やGamma Rayの創設者でギタリストでボーカルのKai Michael Hansen 等の名も見え、その後も元KamelotのRoy Khanや Symphony XのRussell Allen 創設時RainbowのJoe Lynn Turner Ritchie Blackmoreの夫人でBlackmore's NightのCandice Night 等、またインストメンタル・プレヤーとしては、Gamma RayのギタリストHenjo Richter、HelloweenのベーシストのMarkus Grosskopf、イタリアのシンフォニック・メタル・バンドのRhapsody of Fireの元メンバーであるドラムのAlex Holzwarth、90年代以降の Kiss のドラムEric SingerやScorpions創設メンバーでギタリストのRudolf Schenker 等、世界のメタル界を代表する爽々たる面々の名が並んでいたのです。
こうなると、Tobias Sammet率いるこのプロジェクト、やはりその出発点から聴いて見なければという思いがますます強くなり、とうとう手に入れてしまっのが、この作品だったという訳なのです。
そして、聴いみての感想は、
どの曲も似たような感じで聴き終えて印象に残るものがなにもなかったと感じるメタル作品が少なくない中、それぞれ曲に明瞭な個性が感じられ、場面々のイメージが映像となって浮かんでくる展開は、まさにメタルオペラという名を冠するに値するものだったというのが、その感想。
しかしその感覚、その微細には、言葉だけではなかなか語り尽くせない、ということでやはりここで1曲、そのインプレッション、聴いていただき感じていただこうかと思います。
お聴きいただく曲は”Sign Of The Cross”です。
ここ近年で私のさもお気に入りのメタルとなった、このAvantasia。
私事かもしれませんが、あらためてジャーマン・メタルの底力、今年は心底思い知らされることなったような気がしています。
この分では私のとって来年も、このAvantasia、さらに続けて聴きあさる事になりそうです。
さて、2つ目の作品は。
次は、プログレシッブ・ロックの作品から
こちらもAvantasia同様、最近よく聴いているバンドの一つである英国のプログレシッブ・バンドのBig Big Train。
その彼らの作品で、今回選んだのは、2017年発表の彼らの9作目となる”Folklore”です。
このバンド、私としては、以前からその名は知ってはいたのですが、いかんせん彼らの作品のアルバム・ジャケットのデザインが好きなれないというサウンドと無関係な理由から、聴くのをためらい続けることしまっていたのです。
ところが、今年になって自分にフィットするロック作品を探すもなかなか見つけることが出来ずに行き詰っていたことから、ジャケットは気に入らないけど、試にプログレッシブ・ロックの本場、英国のバンド、もしかするとという思いで、ならば一度聴いてみるかとの軽い調子そのサウンドに耳を傾けたところ、それが見事に私の好みにフィットしてしまい、完全に彼らの世界に惹きこまれてしまうことになってしまったのです。
1曲々が異なった表情を持つ豊かな曲想、ロック・バンドでは数少ないフルートやヴァイオリンなどのプレヤーを配した緻密で繊細な表現力豊かなサウンド。
プログレシッブ・ロック隆盛の70年代より数多くのプログレシッブ・ロック・バンドを聴いていた私ですが、その完成度の高さは絶品の感が漂うもの。
また加えて、往年のプログレシッブ・ロックでは珍しいヴォーカル・ハーモニーの美しさは、効果的で聴く者の心を労わり優しく包み込み行くような優しさを感じるなど、そうしたことから、これぞ私の望んでいた究極のプログレとの思いを深くすることになっってしまったのです。
それでは、そうした彼らのサウンドここで1曲、聴いてみて下さい。
曲は、本作品の表題曲”Folklore”です。
本作をはじめ彼らの作品のいくつかを聴いて感じたのは、曲中のところどころに70年代を席巻したGenesis、Jethro Tull、CamelそしてPink Floyd等の、往年のプログレのスパースター達の音の断片がさりげなく散りばめられているように感じ、思わずニンマリ、しかし、聴き終われば彼ら独自の音世界の中浸っていた自分に気付くことしばし、70年代以来、本当に久々に出会った私の待ち望んでいた好みのプログレ・サウンド、先のAvantasiaと共に、来年も嵌り続けることになりそうです。
そして、最後の作品は、
前2作の嵌り初め続きの後は、さらに私がロックを聴き始めて以来、数十年間、嵌り続けぱっなしのこの方の作品から。
keith richards talk is cheap keith richards
写真を見て、もうお分かりですね。
そう、Rollinng Stonesギタリスト、Keith Richardsですね。
とは言っても、これはRollinng Stonesの作品ではなくて、これは、Keith Richards 1988年の制作のファースト・ソロ作品である”Take Is So Hard”。
Keithという人、これまでRollinng Stonesの中で、Mich Jaggerのバックでのバッっキング・ヴォーカルを務めていることはよく知られていますけど、実はそれだけはでなく、僅かではあるもリード・ヴォーカルをとった曲も発表してきているのです。
そうしたStonesの中で彼のリード・ヴォーカル、私の場合、その味に嵌ったのは、Stonesの1972年の作品”Exile On Main Street(邦題;メインストリートのならず者)”の中の”Happy”という曲での、その渋くニヒル漂う、いかにもロックン・ローラーとうべきヴォーカルのカッコ良さが忘れられず、以来、意識の奥底にKeith のソロ・ヴォーカル曲を聴いてみたいな思いが宿り続けていたもの。
それが今年、これも自分にフィットするロック作品が見つけようとして、何かないかとパラパラとネットのぺーいををめくり探していたところ突然目に飛び込んで来たのがこの作品で、思わず意識の奥底にあった願望が蘇り即Getしてしまったのがこの作品だったのなのです。
さて、この作品、聴いてみるとサウンド全体としては表面的にはStonesを連想させてしまうものなのですけど、よくMickがリードをとる本来のStonesサウンドと聴き比べてみると、ギターの乗りはStonesであるけれど、前者がR&B的なものを感じるのに対し、全体としてはソリッド感が強くよりロックン・ロール的色彩が濃いく感じられるように思うのです。
そう感じるのは、やはりMickに相似しているよう感じるKeith のヴォーカル、しかし、本質的には異なるその個性にその因であるようで、Mickのヴォーカルにある粘りっこさに変わって、Keithの渋くニヒル漂うヴォーカルが、そうした印象を生んでいるように思うのです。
それでは、Keithの歌うロックン・ロール色濃いStonesサウンドから1曲聴いてみましょう。
曲は、”Take It So Hard”です。
だいぶ昔のことになりますが、私はMickの来日ソロ・ライブを見たことがあるのですが、そこで感じたMickが歌っっていたStnesナンバーの大いなる違和感のこと。
ヴォーカルはMickなれど、なにか妙に明るくてStonesと全く異なったフィーリング、そこに嫌悪、不快感すら覚えた思い出があるのです。
こう考えると、唯一無二と言われるStonesのサウンドは、MickとKeithの独特な個性にCharlie Wattsの重く正確なリズムを刻むドラムが絡み 生まれ出てたもの。
このKeithのソロ作品を聴いてみると、そこのことをあらためて強く感じます。
それにしても、Keithは見て暮れは当然、サウンドのカッコ良さも抜群。
年とる毎に、男のカッコ良さが滲み出て来るような、70歳を過ぎた写真の彼もそうでした。
こうした年取り方、私も彼にあやかりたいものだと、聴きながらそんなことを考えてしまいました。
それでは、最後にこの作品から、Keithの渋いロッカー・バラード” Make no mistake”で令和初年の音楽談義を締め括ることにしたいと思います。
来るべき令和2年も良い年でありますように。
Avantasia:The Metal Opera
Track listing
All tracks are written by Tobias Sammet.
1. Prelude
2. Reach Out for the Light
3. Serpents in Paradise
4. Malleus Maleficarum
5. Breaking Away
6. Farewell
7. The Glory of Rome
8. In Nomine Patris
9. Avantasia
10. A New Dimension
11. Inside
12. Sign of the Cross
13. The Tower" Kiske
Personnel
Tobias Sammet (Edguy) - Keyboards, Vocals (see "Singers")
Henjo Richter (Gamma Ray) - Guitars
Markus Grosskopf (Helloween) - Bass guitar
Alex Holzwarth (Rhapsody of Fire) - Drums
Guests Musicians
Guitar Jens Ludwig (Edguy) (lead on tracks 12 & 13)
Norman Meiritz (acoustic on track 6)
Keyboards Frank Tischer (Piano on track 11)
Guests Singers
Gabriel Laymann – Tobias Sammet (Edguy) - tracks 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 & 13
Lugaid Vandroiy – Michael Kiske (credited as Ernie) (ex-Helloween, Unisonic) - tracks 2, 5, 6, 9, & 13
Friar Jakob – David DeFeis (Virgin Steele) - tracks 3 & 13
Bailiff Falk von Kronberg – Ralf Zdiarstek - tracks 4 & 7
Anna Held – Sharon den Adel (Within Temptation) - track 6
Bishop Johann von Bicken – Rob Rock (ex-Axel Rudi Pell, Driver, Impellitteri) - track 7 & 12
Pope Clement VIII – Oliver Hartmann (ex-At Vance) - tracks 7, 12 & 13
Elderane the Elf – Andre Matos † (ex-Symfonia, ex-Shaaman, ex-Angra, Viper) – tracks 11, 12 & 13
Regrin the Dwarf – Kai Hansen (Gamma Ray, ex-Helloween) - tracks 11 & 12
Voice of the Tower – Timo Tolkki (ex-Symfonia, ex-Revolution Renaissance, ex-Stratovarius) - track 13
Recorded
2000 Rhoen Studios, Germany
Big Big Train:Folklore
Track listing
1. Folklore -David Longdon-
2. London Plane -Greg Spawton-
3. Along the Ridgeway -Spawton-
4. Salisbury Giant -Spawton-
5. The Transit of Venus Across the Sun -Spawton-
6. Wassail -Longdon-
7. Winkie -Longdon-
8. Brooklands -Spawton-
9. Telling the Bees -Longdon-
Personnel
David Longdon - lead vocals, flute, acoustic guitar, mandolin, percussion
Nick D'Virgilio - drums, percussion, backing vocals
Greg Spawton - bass guitar, bass pedals, acoustic guitar, backing vocals
Andy Poole - acoustic guitar, mandolin, keyboards, backing vocals
Dave Gregory - electric guitars
Danny Manners - keyboards, double bass
Rachel Hall - violin, viola, cello, backing vocals
Rikard Sjöblom - keyboards, electric guitars, accordion, backing vocals
Released
27 May 2016
keithe Richards:Take Is So Hard
Track listing
All songs by Keith Richards and Steve Jordan.
1.Big Enough
2.Take It So Hard
3.Struggle
4.I Could Have Stood You Up
5.Make No Mistake
6.You Don't Move Me
7."How I Wish
8.Rockawhile
9.Whip It Up
10.Locked Away
11.It Means a Lot
Personnel
The X-Pensive Winos
Keith Richards – lead vocals, guitar
Steve Jordan – drums, percussion, bass on 'Take It So Hard', backing vocals
Sarah Dash – backing vocals, duet on "Make No Mistake"
Charley Drayton – bass guitar, drums on 'Take It So Hard'
Ivan Neville – piano, keyboards
Bobby Keys – tenor saxophone on "I Could Have Stood You Up" and "Whip It Up"
Waddy Wachtel – acoustic, electric, and slide guitar, production consultant
Additional musicians
Bootsy Collins – bass guitar on "Big Enough"
Michael Doucet – violin on "Locked Away"
Stanley "Buckwheat" Dural – accordion on "You Don't Move Me", "Rockawhile" and "Locked Away"
Johnnie Johnson – piano on "I Could Have Stood You Up"
Chuck Leavell – organ on "I Could Have Stood You Up"
Maceo Parker – alto saxophone on "Big Enough"
Joey Spampinato – bass guitar on "I Could Have Stood You Up" and "Rockawhile"
Mick Taylor – guitar on "I Could Have Stood You Up"
Bernie Worrell – organ on "Big Enough" and "You Don't Move Me", clavinet on "Make No Mistake" and "Rockawhile"
Jimmi Kinnard – bass guitar on "Make No Mistake"
Patti Scialfa – backing vocals
The Memphis Horns – horns
Willie Mitchell – horn arrangements
Recorded
August 1987 – May 1988
PS.
令和元年の今年で印象に残り感じたこと。
それは、昭和、平成、そして令和と3代の天皇を見て来た私にとって、この令和のさまざま新天皇の即位の儀式に対し、それに接する国民の態度の対応の新旧における大きな違いこと。
昭和の天皇は、戦後国民の象徴となったとは言え、その責務を果たそうするも、自身があの戦争渦中にあってそれを阻止出来なかった回顧の思いからか、今一つ国民とは別次元の存在を払拭出来なかったように思え、その後、そうした名残が現上皇様、天皇即位の際もまだ多分に残っていたよう感じたのに対し、今年の現天皇の即位の折は、真に国民の中にその存在が根付き定着していたと感じたこと。
一昔前のように天皇は神ではなく(あれは、欧米先進国の侵略を防ぐ強い集権国家を作るための明治の元勲たちの知恵から生まれた歴史的必然性だったと考えるのですが。)、平和、この国の人々の安定した生活を営むためシンボルとして、その存在が定着したということではと感じ、これからもそうあり続けて欲しいとの願いをあらたした。
たかが30年間なのに、その行動考え方次第で、自分を含め人々の思いがここまで変わるものだということを知らされたこと、これは本当に大きな心の収穫でした。
2019年!印象に残った作品;Jazz-Anoter Instmental & Vocal編 [音源発掘]
長かった入院生活からも、無事解放。
今は日常を取り戻すべくリハビリ、療養中となったところで当ブログも、再開の運びとなりました。
前回は、これから入院、当ブログもしばらくお休みということもあって、例年より少し早めであるけれど一年の締め括りとして”2019年!印象に残った作品”の第一弾としてジャズ・ピアノの作品を取上げ語らさせていただきましたが、今回は引き続きその第2弾。
ピアノ以外の楽器によるジャズ作品と、同じくヴォーカルの作品を選び語ることにしたいと思います。
しかし........
そうは決めたものの、いざ、どの作品をチョイスするかの段になって、今年は例年に増して多くの作品に接しすることが出来、その分印象に残った作品が多かったことから、困ったことに、今度はその中からさらに3作品程度に絞り込み選ぶとなると、それを決めきるのはなかなか難しくなってしまう始末。
とは言いながらもなにが幸いするかわからないもので、そこに訪れたのが病院のベットの上で過ごすことになった入院生活。
何もすることがなく時間を持て余し退屈であったことから、ならばと言う訳でそれらの作品を再度聴き直し、選択肢を絞ることにしたのです。
そうして、選んだのが以下の3作品。
まずは、日本のテナー・サックス奏者 中村誠一の
1973年の作品、”First Contact”から。
この作品、今年たまたまビデオデッキを手に入れたことから、我がのライブラリーにお蔵に入りしていた平成の初めのライブ映像のデジタル化しようとその作業をする中で、この中村誠一が、日本のジャズ史上名高いジョージ川口とビッグ4の後継であるニュー・ビッグ4のメンバーとしてのプレーしている映像を発見、デビュー当初はピアニストの山下洋輔トリオのメンバーとして、フリーなプレーに徹していた彼が、客演で同カルテットに参加していたテナー・サックス奏者の松本英彦と共にオ-ソドックスの香り高いジャズを歌い上げているのを見て、そのリーダー作品が聴きたくなり調べ手に入れたのが本作だったのです。
この作品、中村誠一ソロ転向後の初リーダー作品なのですが、発表当時は、それまでの山下洋輔トリオで演じたフリージャズのスタイルから一転して、オーソドックスな演奏に変貌した意外なその姿が話題を呼んだものっだったのだとか。
しかし、今あの時代を振り返ってみると、本場アメリカでは、60年代後半のフリー・ジャズの行き詰まりから次の時代へのジャズを模索する動きの中で生まれたロック等の要素を取り入れた、その多くが今にいうファンクやフュージョンへの方向へと進む中、日本で次の時代に引き継がれるべき本来のジャズの伝統を汲むこうしたジャズが生まれていたこと、その動きが本場アメリカの場合、70年代後半以降であったことを考え合わせると、あらためて日本人の優れた感性と先見性に喝采を送りたくなってしまうのです。
それでは、ここでこの作品から1曲、お聴きいただき、その素晴らしい感性、じっくりと味わっていただこうかと思います。
曲は美しいバラード曲、”Everything Happens To Me ”です。
実はビデオ編集時に中村誠一のプレイに興味が湧き、彼の経歴ついて調べていたところ、インタビューに答える形でその生い立ちにについて彼自身が語っていた記事を見つけ読んだのですが、それによるとフリー・ジャズをやめたのは、フリーを演じるエネルギーがなくなって来たからなのだとのこと。
そしてソロ転向後に、ジョージ川口に誘われ、いきなりそれまで演奏したことない曲を演奏させられることになったことから、思い切り滅茶苦茶にプレイをし首になると思ったら、レギュラーの座を射止めてしまったという、自分に正直かつ無手勝流で成功を収めてしまったとのことが語られていたのです。
そうしたことから、本作のこの演奏も、そうした彼の音楽に対する生き方から生まれた、それが既成の伝統に捉われない今にも通じる、新鮮さを保ち続けている大きな要因なのでは考えされてしまうのです。
さて、続いての作品は..........
今年は妙にフルートが主体となる作品が聴きたくて、こちらもいろいろ探してみたのですが、フルートと言うと、どうもその軽快でナチュラルなそのサウンドが災いしてか、フュージョン色が濃い作品ばかりになりがちで、これまで、なかなか本来のジャズらしさを持った作品を見つけられないでいたのです。
そこで今年は何としてもジャズらしさのあるフルート作品を掘り出そうと考えた挙句、70年代の初めChick Coreaの率いるグループのReturn To Foreverで、フュージョンとは言えジャズの伝統を宿したサウンドの上を、美しく聴き応えのあるフルート・プレイで駆け抜け聴かせてくれていたJoe Farrellのことを思い出し、もしかするとと思い、その彼の作品に焦点当て探した結果見つけたのがこの作品だったのです。
それがこの作品、1976年発表の”Benson & Farrell”です。
この作品、タイトルにある通り、ギターのGeorge Bensonとリード奏者Joe Farrellのコラボによる作品なのですが、そこでギターを務めるBensonも、Wes Montgomeryの後継者という鳴物入りで登場、登場直後はMiles Davis、1968年発表の作品”Miles in the sky”の中の”Paraphernalia”でその評判通りのプレイを聴かせてくれていたものの、その後は彼の属していたCTIレコードの意向か、急速にフュージョン化、挙句果てには達者なヴォーカルでソウル・フュージョン化、そこで多くの人気を獲得するに至るも、反面、彼自身のギター・プレーの醍醐味が希薄となり、私のようなデビュー当時の彼の素晴らしギター・プレーを知る者にとっては、かなり残念に思いを持っていたのです。
そうこうする中、出会うことが出来たこの作品、Farrellとの組み合わせならばBensonも、 初期Corea的雰囲気に包まれたフュージョン・サウンド中で、縦横無尽にギタ―・ソロを繰り広げているのではないかという淡い期待を抱き早速入手、聴いてみることにしたのです。
そして、その結果は...........
というところで、1曲、その演奏、聴いていただきその答え探っていくことにいたしょう。
曲は、Farrellの爽やかかつ軽快なフルートが心地良い”Flute Song”です。
CTIレコード制作の作品には珍しく、同社の他の作品に見られるオーバーな演出もなく単なるイージーリスニングに終始することないサウンド造りがなされているように感じるこの演奏、クレジットを見ればそのアレンジを手掛けているのはDavid Matthews とのこと。
後年、Manhattan Jazz Quintetのリーダーとして、原曲の良さも保ちつつ一味違うアレンジを施した楽曲を、同Quintetに提供して来たMatthews の真骨頂が、既にここでも大いに発揮されているのを感じます。
そして、そこでプレイをするBenson と Farrellも、リックスした雰囲気の中、熱いソロを繰り広げている、私としては、緊張感溢れるジャズ・サウンドもいいけれど、時にはこうしたゆったりとした気分で、それぞれの秘儀を駆使したソロに浸れる、こうしたサウンドも良いものだと思っているのですが、いかがだったでしょうか。
そしてラストは、
ヴォーカル作品から。
今度は、70年代、”Killing Me Softly With His Song(邦題;やさしく歌って””で一世を風靡した女性ヴォーカリストのこんな作品をチョイスしてみました。
その作品は、Roberta Flack の2012年の作品”Let It Be: Sings the Beatles ”
文字通り、Robertaによる The Beatles の楽曲のカバー集です。
彼女、これまで自己のアルバムの中で、Bob DylanやSimon & Garfunkelの楽曲を取り上げカバーして来ているのですが、デビュー以前は教会のオルガニストをしていた時もあったとかで、そのぜいかこれら楽曲も、静謐なゴスペル的アプローチで淡々と歌い上げていたその印象が私の心に深く残っていて、そのことからこの作品、果たしてRobertaがBeatles をどう料理し聴かせてくれるのかという興味と、デビュー以来50年近くを歩んできた彼女の円熟の境地を確かめてみたいという思いから手にし聴いたもの。
そうして聴いてみると、詳細な録音時期は不明なるも、この作品が発表された2012年というと、彼女の年齢は既に75歳であったはず、この年齢になる歌手の多くが声量の衰えから、引退もしくは、それをテクニックでカバーし枯れた味わいを醸し出すことで新境地を切り開いたりする等の例が多い中、彼女の場合、その歌声は往時のまま、それに加えて年輪を重ねたことから生まれる新たなアプローチでそれらを歌い上げていたことに、いたく感動を覚えることになってしまったのです。
それでは、 そうしたRoberta Flack の歌声、まずはここで 1曲聴いていただき、その年輪の技、聴いてみることにいたしましょう。
曲は”In My Life ”です。
カラフルかつ軽やかなリズムに彩られた”In My Life ”、そこから聴こえる彼女の歌声は、若々しさを通り越して初々しささえ感じます。
実際、全曲聴いてみて、聴きなれたBeatles の楽曲に、こんなアプローチがあったのかと思うことしばし、さすがRoberta というところです。
それにしても、ここまで言って、この1曲だけで終わるのはなんとも無責任、そんな訳で続けてもう1曲聴ききながら、今回のお話ここで締め括ることにしたいと思います。
曲は、Beatles の初期のバラード曲から、”If I Fell”です。
早いもので、いよいよ年の瀬、12月。
私にとっては消化器系の不調に悩まされ続けた1年でしたけど、年の終わり迫っての入院で、どうやら完調に復せそう。
しばらく、養生しながら年明けには、迷いながらも今回ご紹介出来なかった諸作品をご紹介して行きたいと思います。
最後に、このRoberta の”Oh Darling”で、クールなソウルを味わいながら、じっくりと英気を養うことにしたいと思います。
Seiichi Nkamura-First Contact
Track listing
1.Frank'n Earnest
2.Everything Happens to me
3.Billie's Bounce
4.Melba's Blues
5.Judy's Samba
6.Colsing theme for quintet
Personnel
中村誠一(ts)、,
向井滋春(tb)
田村博(p)
福井五十雄(b)
楠本卓司(ds)
Recorded
1973年12月30日 青山ロブロイ
Benson & Farrell
Track listing
All compositions by David Matthews except as indicated
1.Flute Song
2.Beyond the Ozone
3.Camel Hump
4.Rolling Home
5.Old Devil Moon (Burton Lane, E.Y. "Yip" Harburg)
Personnel
George Benson - guitar
Joe Farrell - flute, bass flute (tracks 1, 3, 5), soprano saxophone (tracks 3 & 4)
Eddie Daniels (tracks 1, 3, 5), David Tofani (tracks 1 & 3) - alto flute
Don Grolnick - electric piano (tracks 1-4)
Sonny Bravo - piano (track 5)
Eric Gale (tracks 1 & 3), Steve Khan (tracks 2 & 4) - guitar
Will Lee (tracks 1-4), Gary King (track 5) - bass
Andy Newmark - drums (tracks 1-4)
Nicky Marrero - percussion
Jose Madera - congas (track 5)
Michael Collaza - timbales (track 5)
David Matthews - arranger
Recorded
January 20 & 21 and March 12, 1976
Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Roberta Flack-Let It Be: Sings the Beatles
Track listing
1 In My Life
2 Hey Jude
3 We Can Work It Out
4 Let It Be
5 Oh Darling
6 I Should Have Known Better
7 The Long And Winding Road Vocals [Duet] – Sherrod Barnes
8 Come Together
9 Isn't It A Pity
10 If I Fell
11 And I Love Him
12 Here, There, And Everywhere
Personnel
Backing Vocals – Jerry Barnes, Katreece Barnes*, Roberta Flack, Sherrod Barnes, Tameka Simone, Vivian Sessoms
Bass – David Williams , Jerry Barnes, Nichlas Branker*, Sherrod Barnes
Drums – Bernard Sweetney, Buddy Williams, Charlie Drayton*, Chris Parks, Kuhari Parker, Ricardo Jordan
Guitar – Dean Brown, Jerry Barnes, Nathan Page, Sherrod Barnes
Keyboards – Barry Miles, Bernard Wright, Morris Pleasure, Roberta Flack, Selan Lerner*, Shedrick Mitchell, Sherrod Barnes
Release
2012
今は日常を取り戻すべくリハビリ、療養中となったところで当ブログも、再開の運びとなりました。
前回は、これから入院、当ブログもしばらくお休みということもあって、例年より少し早めであるけれど一年の締め括りとして”2019年!印象に残った作品”の第一弾としてジャズ・ピアノの作品を取上げ語らさせていただきましたが、今回は引き続きその第2弾。
ピアノ以外の楽器によるジャズ作品と、同じくヴォーカルの作品を選び語ることにしたいと思います。
しかし........
そうは決めたものの、いざ、どの作品をチョイスするかの段になって、今年は例年に増して多くの作品に接しすることが出来、その分印象に残った作品が多かったことから、困ったことに、今度はその中からさらに3作品程度に絞り込み選ぶとなると、それを決めきるのはなかなか難しくなってしまう始末。
とは言いながらもなにが幸いするかわからないもので、そこに訪れたのが病院のベットの上で過ごすことになった入院生活。
何もすることがなく時間を持て余し退屈であったことから、ならばと言う訳でそれらの作品を再度聴き直し、選択肢を絞ることにしたのです。
そうして、選んだのが以下の3作品。
まずは、日本のテナー・サックス奏者 中村誠一の
1973年の作品、”First Contact”から。
この作品、今年たまたまビデオデッキを手に入れたことから、我がのライブラリーにお蔵に入りしていた平成の初めのライブ映像のデジタル化しようとその作業をする中で、この中村誠一が、日本のジャズ史上名高いジョージ川口とビッグ4の後継であるニュー・ビッグ4のメンバーとしてのプレーしている映像を発見、デビュー当初はピアニストの山下洋輔トリオのメンバーとして、フリーなプレーに徹していた彼が、客演で同カルテットに参加していたテナー・サックス奏者の松本英彦と共にオ-ソドックスの香り高いジャズを歌い上げているのを見て、そのリーダー作品が聴きたくなり調べ手に入れたのが本作だったのです。
この作品、中村誠一ソロ転向後の初リーダー作品なのですが、発表当時は、それまでの山下洋輔トリオで演じたフリージャズのスタイルから一転して、オーソドックスな演奏に変貌した意外なその姿が話題を呼んだものっだったのだとか。
しかし、今あの時代を振り返ってみると、本場アメリカでは、60年代後半のフリー・ジャズの行き詰まりから次の時代へのジャズを模索する動きの中で生まれたロック等の要素を取り入れた、その多くが今にいうファンクやフュージョンへの方向へと進む中、日本で次の時代に引き継がれるべき本来のジャズの伝統を汲むこうしたジャズが生まれていたこと、その動きが本場アメリカの場合、70年代後半以降であったことを考え合わせると、あらためて日本人の優れた感性と先見性に喝采を送りたくなってしまうのです。
それでは、ここでこの作品から1曲、お聴きいただき、その素晴らしい感性、じっくりと味わっていただこうかと思います。
曲は美しいバラード曲、”Everything Happens To Me ”です。
実はビデオ編集時に中村誠一のプレイに興味が湧き、彼の経歴ついて調べていたところ、インタビューに答える形でその生い立ちにについて彼自身が語っていた記事を見つけ読んだのですが、それによるとフリー・ジャズをやめたのは、フリーを演じるエネルギーがなくなって来たからなのだとのこと。
そしてソロ転向後に、ジョージ川口に誘われ、いきなりそれまで演奏したことない曲を演奏させられることになったことから、思い切り滅茶苦茶にプレイをし首になると思ったら、レギュラーの座を射止めてしまったという、自分に正直かつ無手勝流で成功を収めてしまったとのことが語られていたのです。
そうしたことから、本作のこの演奏も、そうした彼の音楽に対する生き方から生まれた、それが既成の伝統に捉われない今にも通じる、新鮮さを保ち続けている大きな要因なのでは考えされてしまうのです。
さて、続いての作品は..........
今年は妙にフルートが主体となる作品が聴きたくて、こちらもいろいろ探してみたのですが、フルートと言うと、どうもその軽快でナチュラルなそのサウンドが災いしてか、フュージョン色が濃い作品ばかりになりがちで、これまで、なかなか本来のジャズらしさを持った作品を見つけられないでいたのです。
そこで今年は何としてもジャズらしさのあるフルート作品を掘り出そうと考えた挙句、70年代の初めChick Coreaの率いるグループのReturn To Foreverで、フュージョンとは言えジャズの伝統を宿したサウンドの上を、美しく聴き応えのあるフルート・プレイで駆け抜け聴かせてくれていたJoe Farrellのことを思い出し、もしかするとと思い、その彼の作品に焦点当て探した結果見つけたのがこの作品だったのです。
それがこの作品、1976年発表の”Benson & Farrell”です。
この作品、タイトルにある通り、ギターのGeorge Bensonとリード奏者Joe Farrellのコラボによる作品なのですが、そこでギターを務めるBensonも、Wes Montgomeryの後継者という鳴物入りで登場、登場直後はMiles Davis、1968年発表の作品”Miles in the sky”の中の”Paraphernalia”でその評判通りのプレイを聴かせてくれていたものの、その後は彼の属していたCTIレコードの意向か、急速にフュージョン化、挙句果てには達者なヴォーカルでソウル・フュージョン化、そこで多くの人気を獲得するに至るも、反面、彼自身のギター・プレーの醍醐味が希薄となり、私のようなデビュー当時の彼の素晴らしギター・プレーを知る者にとっては、かなり残念に思いを持っていたのです。
そうこうする中、出会うことが出来たこの作品、Farrellとの組み合わせならばBensonも、 初期Corea的雰囲気に包まれたフュージョン・サウンド中で、縦横無尽にギタ―・ソロを繰り広げているのではないかという淡い期待を抱き早速入手、聴いてみることにしたのです。
そして、その結果は...........
というところで、1曲、その演奏、聴いていただきその答え探っていくことにいたしょう。
曲は、Farrellの爽やかかつ軽快なフルートが心地良い”Flute Song”です。
CTIレコード制作の作品には珍しく、同社の他の作品に見られるオーバーな演出もなく単なるイージーリスニングに終始することないサウンド造りがなされているように感じるこの演奏、クレジットを見ればそのアレンジを手掛けているのはDavid Matthews とのこと。
後年、Manhattan Jazz Quintetのリーダーとして、原曲の良さも保ちつつ一味違うアレンジを施した楽曲を、同Quintetに提供して来たMatthews の真骨頂が、既にここでも大いに発揮されているのを感じます。
そして、そこでプレイをするBenson と Farrellも、リックスした雰囲気の中、熱いソロを繰り広げている、私としては、緊張感溢れるジャズ・サウンドもいいけれど、時にはこうしたゆったりとした気分で、それぞれの秘儀を駆使したソロに浸れる、こうしたサウンドも良いものだと思っているのですが、いかがだったでしょうか。
そしてラストは、
ヴォーカル作品から。
今度は、70年代、”Killing Me Softly With His Song(邦題;やさしく歌って””で一世を風靡した女性ヴォーカリストのこんな作品をチョイスしてみました。
その作品は、Roberta Flack の2012年の作品”Let It Be: Sings the Beatles ”
文字通り、Robertaによる The Beatles の楽曲のカバー集です。
彼女、これまで自己のアルバムの中で、Bob DylanやSimon & Garfunkelの楽曲を取り上げカバーして来ているのですが、デビュー以前は教会のオルガニストをしていた時もあったとかで、そのぜいかこれら楽曲も、静謐なゴスペル的アプローチで淡々と歌い上げていたその印象が私の心に深く残っていて、そのことからこの作品、果たしてRobertaがBeatles をどう料理し聴かせてくれるのかという興味と、デビュー以来50年近くを歩んできた彼女の円熟の境地を確かめてみたいという思いから手にし聴いたもの。
そうして聴いてみると、詳細な録音時期は不明なるも、この作品が発表された2012年というと、彼女の年齢は既に75歳であったはず、この年齢になる歌手の多くが声量の衰えから、引退もしくは、それをテクニックでカバーし枯れた味わいを醸し出すことで新境地を切り開いたりする等の例が多い中、彼女の場合、その歌声は往時のまま、それに加えて年輪を重ねたことから生まれる新たなアプローチでそれらを歌い上げていたことに、いたく感動を覚えることになってしまったのです。
それでは、 そうしたRoberta Flack の歌声、まずはここで 1曲聴いていただき、その年輪の技、聴いてみることにいたしましょう。
曲は”In My Life ”です。
カラフルかつ軽やかなリズムに彩られた”In My Life ”、そこから聴こえる彼女の歌声は、若々しさを通り越して初々しささえ感じます。
実際、全曲聴いてみて、聴きなれたBeatles の楽曲に、こんなアプローチがあったのかと思うことしばし、さすがRoberta というところです。
それにしても、ここまで言って、この1曲だけで終わるのはなんとも無責任、そんな訳で続けてもう1曲聴ききながら、今回のお話ここで締め括ることにしたいと思います。
曲は、Beatles の初期のバラード曲から、”If I Fell”です。
早いもので、いよいよ年の瀬、12月。
私にとっては消化器系の不調に悩まされ続けた1年でしたけど、年の終わり迫っての入院で、どうやら完調に復せそう。
しばらく、養生しながら年明けには、迷いながらも今回ご紹介出来なかった諸作品をご紹介して行きたいと思います。
最後に、このRoberta の”Oh Darling”で、クールなソウルを味わいながら、じっくりと英気を養うことにしたいと思います。
Seiichi Nkamura-First Contact
Track listing
1.Frank'n Earnest
2.Everything Happens to me
3.Billie's Bounce
4.Melba's Blues
5.Judy's Samba
6.Colsing theme for quintet
Personnel
中村誠一(ts)、,
向井滋春(tb)
田村博(p)
福井五十雄(b)
楠本卓司(ds)
Recorded
1973年12月30日 青山ロブロイ
Benson & Farrell
Track listing
All compositions by David Matthews except as indicated
1.Flute Song
2.Beyond the Ozone
3.Camel Hump
4.Rolling Home
5.Old Devil Moon (Burton Lane, E.Y. "Yip" Harburg)
Personnel
George Benson - guitar
Joe Farrell - flute, bass flute (tracks 1, 3, 5), soprano saxophone (tracks 3 & 4)
Eddie Daniels (tracks 1, 3, 5), David Tofani (tracks 1 & 3) - alto flute
Don Grolnick - electric piano (tracks 1-4)
Sonny Bravo - piano (track 5)
Eric Gale (tracks 1 & 3), Steve Khan (tracks 2 & 4) - guitar
Will Lee (tracks 1-4), Gary King (track 5) - bass
Andy Newmark - drums (tracks 1-4)
Nicky Marrero - percussion
Jose Madera - congas (track 5)
Michael Collaza - timbales (track 5)
David Matthews - arranger
Recorded
January 20 & 21 and March 12, 1976
Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Roberta Flack-Let It Be: Sings the Beatles
Track listing
1 In My Life
2 Hey Jude
3 We Can Work It Out
4 Let It Be
5 Oh Darling
6 I Should Have Known Better
7 The Long And Winding Road Vocals [Duet] – Sherrod Barnes
8 Come Together
9 Isn't It A Pity
10 If I Fell
11 And I Love Him
12 Here, There, And Everywhere
Personnel
Backing Vocals – Jerry Barnes, Katreece Barnes*, Roberta Flack, Sherrod Barnes, Tameka Simone, Vivian Sessoms
Bass – David Williams , Jerry Barnes, Nichlas Branker*, Sherrod Barnes
Drums – Bernard Sweetney, Buddy Williams, Charlie Drayton*, Chris Parks, Kuhari Parker, Ricardo Jordan
Guitar – Dean Brown, Jerry Barnes, Nathan Page, Sherrod Barnes
Keyboards – Barry Miles, Bernard Wright, Morris Pleasure, Roberta Flack, Selan Lerner*, Shedrick Mitchell, Sherrod Barnes
Release
2012